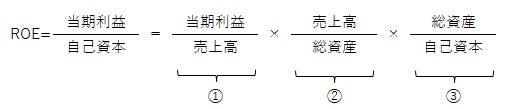10月27日の日経平均株価は初めて5万円の大台を突破しました。28日の日経新聞はコラム記事(スクランブル)で次のように伝えています。「けん引役は人口知能(AI)ブームの追い風を一身に受けるソフトバンクグループ(SBG)だ。」「……売り手が踏み上げられて上昇の勢いはしばらく収まりそうにない。」また、外資系証券会社のコメントとして「ものすごい額を売買している著名な個人投資家やその影響を受けた個人の売買シェアが高くなっているように感じる。」と紹介しています。ここでいう著名な個人投資家とは、いうまでもなく日経平均を動かす男=cisさんでしょう。
続けて日経新聞は「……空売りのために貸株残高は9月中に215万株とおよそ3年ぶりの高水準になった。……ところが、SBGの上昇に弾みがつくと様相が変わった。売り手が耐えられなくなって持ち高を解消し、買い方も再び持ち高を増やし始めた。貸株残高は10月22日には6万株台まで減少した。」と伝えています。
インフレによる日本株の先高感に加え、貸株市場の歪な需給に着目したcisさんが、機関投資家顔負けの大ロットでSBG株に買いを入れたのでしょう。売り方はパニック状態です。損失が~とか言ってるひまはありません。逃げ遅れたら骨まで焼かれてしまいます。目をつぶってSBG株を買い戻すしかないのです。
ただ、忘れてはならないのはcisさんは私たちのような長期投資家ではないことです。間違いなく、どこかのタイミングで利益確定の大量の売りを出してきます。それがいつなのか。インフレ、AIブームはこれからも株式市場の上昇を支えるでしょうが、短期的にはいつ調整が入ってもおかしくないと思います。
【株】いつまで続く日経株高