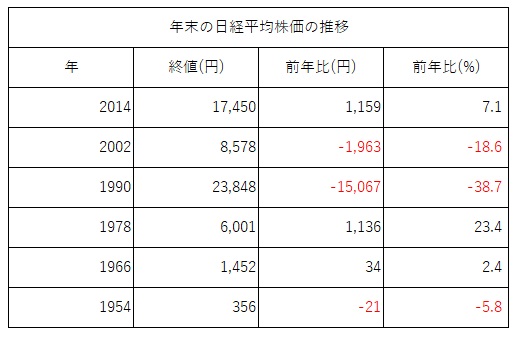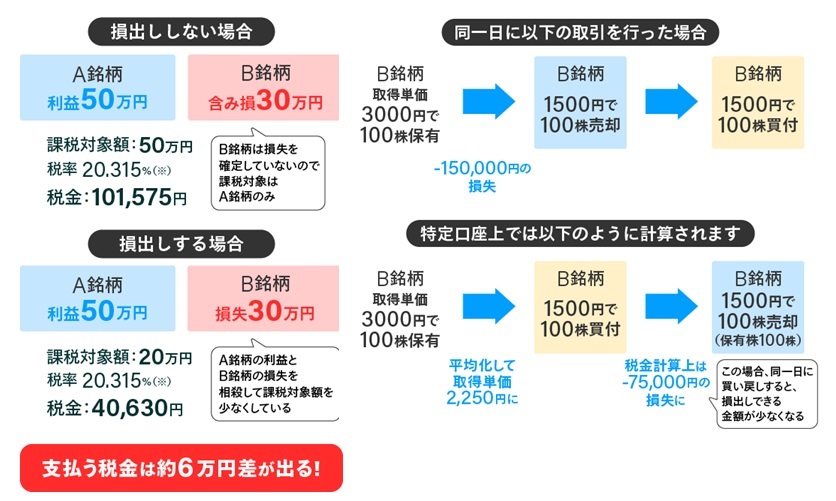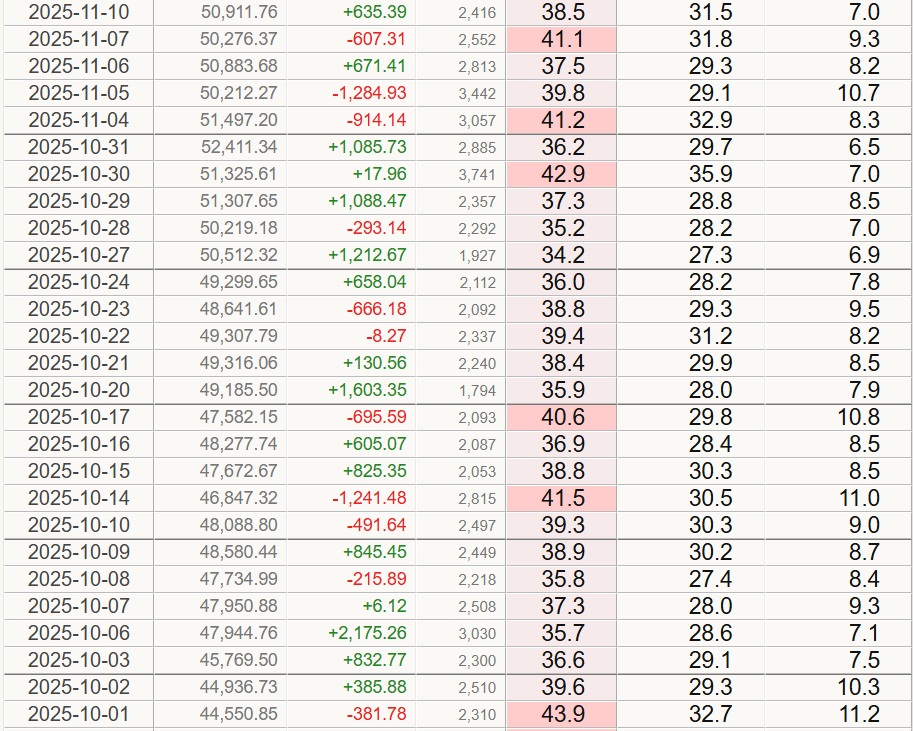足下のドル円の動きに翻弄されたFX投資家は多いのではないでしょうか。1月23日、日本の通貨当局は為替介入の前段階となるレートチェックを実施しました。円安に歯止めをかけるための協調行動です。高市首相が消費減税の検討を表明したのを機に円安が急速に進行し、23日には1ドル=160円に迫りました。このタイミングで例のレートチェックです。ただ、通常は日銀の単独行動となるのですが、今回はNY連銀からもレートチェックが入ったというので、市場関係者はパニックに襲われたわけです。一転、円は円高に転じ、一時153円79銭を付けました。日米協調でのレートチェックは、ベッセント米財務長官がダボス会議の経済フォーラム年次総会に同席していた片山財務大臣に持ちかけたものと見られています。トランプ大統領も予てドル安を歓迎しています。
ところが、28日の米CNBCのインタビューでベッセント長官は「為替に介入していない」と発言、日米協調のレートチェックを否定しました。これにより、NY時間ではドル円は156円台に下落しました。そして、同長官は「米国は常に強いドル政策をとってきた」とも語り、米当局が過度なドル安を許容しない態度を示しました。
(しかし、29日の東京市場では1ドル=153円前半まで円高が進行しています。)
この2枚舌とも言うべきベッセント長官に対し、私たち個人投資家はこう文句を言いたくなります。ベッセント長官。あんたええ加減にせーや。円高ドル安か、円安ドル高か、いったいどっちやねん?
為替を触っている個人投資家の皆さん、これが為替の怖いところです。為替相場は購買力平価だの、実質金利差だの、需給だのといったファンダメンタルズに関係なく、ある日突然、政治的な力でかき乱されます。株式市場や債券市場では起きないことが、為替市場では普通に起きるのです。これを理不尽と嘆いてみても始りません。為替とは所詮そういうものなのです。
【株】ベッセント長官、どっちやねん?