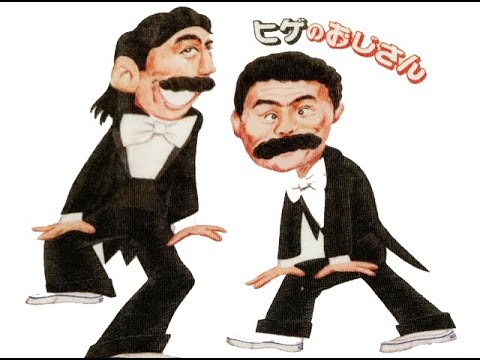相場の予想なんて当たるわけがありません。もしあなたの回りで、したり顔で相場の予想を垂れる輩がいたなら、眉に唾を付けてから聞くことをお薦めします。しかし、日本という国の経済が今後どこへ向かおうとしているのか、そんな大局観について議論することは決して無駄ではないと考えます。
ひとつ参考にしたい本があります。齋藤ジンさんが書かれた「世界秩序が変わるとき」(文春新書)です。齋藤さんは日本のメガバンク出身の投資コンサルタントです。といっても、そこらへんに転がっている自称コンサルとは違って、ヘッジファンドをはじめとした運用のプロたちに助言する超一流のコンサルタントです。そんな齋藤さんが本書で主張するのが、新自由主義の終わりと日本の復活です。どういうことかと言いますと、「新自由主義的な世界観に支えられてきた既存システムは信認を失った。根幹となる世界観への信認が崩れた以上、パラダイムシフトが発生する。その結果、勝者と敗者の入れ替え戦が始り、(今まで負け組であった)日本は勝ち組になる。」というものです。
「日本が勝ち組」と言われても、にわかには信じ難いですが、日本が勝ち組になると齋藤さんが考える根拠は二つあります。ひとつめの根拠は、覇権国家アメリカが中国を封じ込めるため「強い日本」の協力が不可欠になっており、日本経済の成長を後押しする可能性が高いことです。このような地政学上の要請でアメリカが日本をバックアップした事例は過去にもあります。第二次世界大戦後の冷戦下で、アメリカはソ連封じ込めの一環として日本経済の強化を図るため、1ドル=360円という超円安水準に為替を固定するとともに、日本製品の輸出先として米国市場を開放しました。これらのアメリカの支援によって、日本は高度経済成長を果たすことができたのです。
そして、ふたつめの根拠は、日本経済が「失われた30年」というデフレのノルム(常態)から解放されつつあることです。これからの日本では人口減少がインフレ圧力として働いてきます。実際、2025年春闘では昨年に続き力強い賃金上昇が見込まれています。2024年の春闘では中小企業の賃上げも4%を超えました。これが常態化するようであれば、4%アップの賃金を支払う余力のある企業だけが生き残ることになります。
デフレ下で温存されてきたゾンビ企業は淘汰され、銀行に積み上がった家計の貯蓄は株式市場に流れ込み、企業の内部留保は設備投資に回ることでしょう。日本経済の生産性は劇的に改善することが期待されます。
経済成長と株価の動向は短期的には必ずしも一致しませんが、長期的にはある程度パラレルに動きます。日本経済が齋藤さんの見立て通りになるかは分かりません。しかし、個人的にはこのシナリオに乗ってみたい気分です。ていうか、もう乗っています。
【株】日本経済の行方