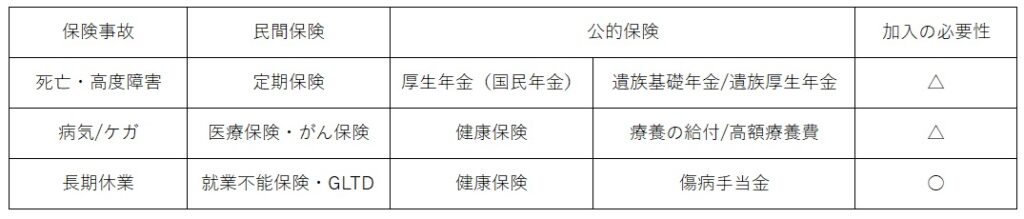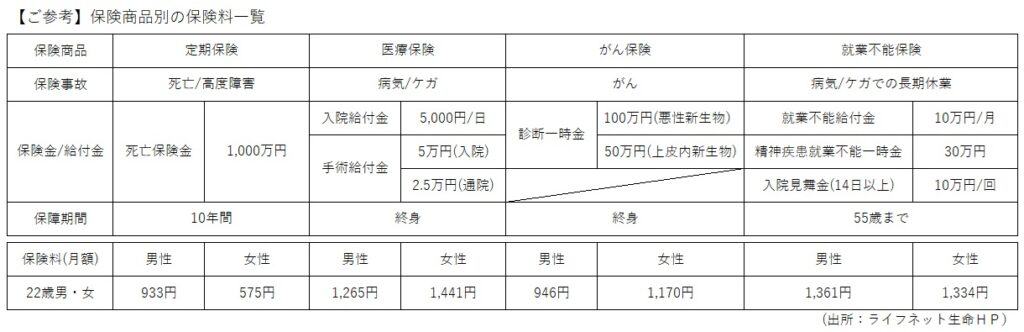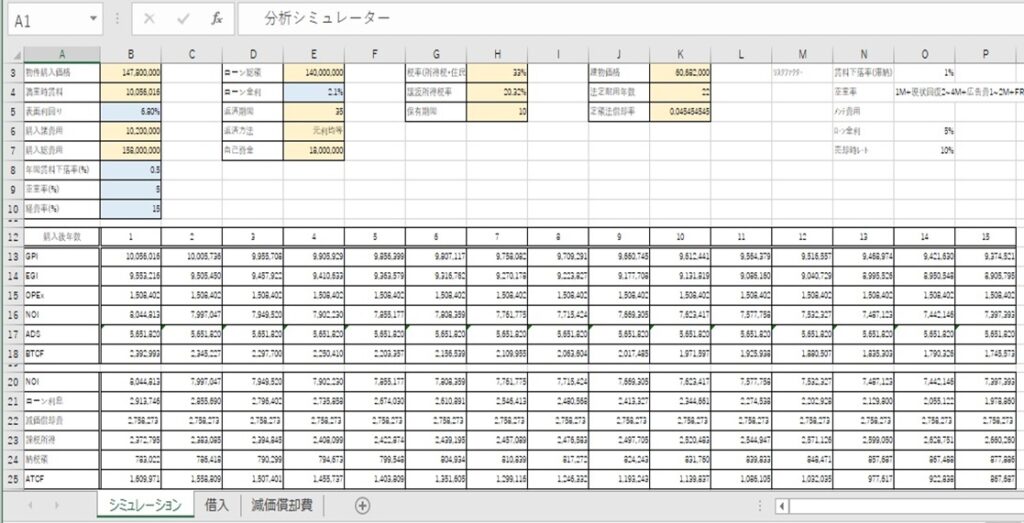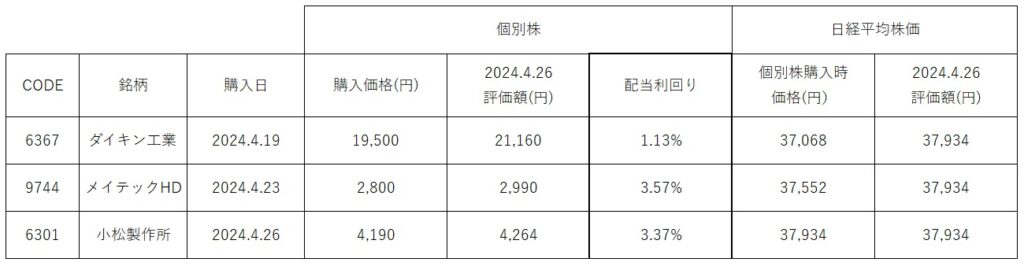2024年は5年に1度の財政検証(※1)の年であり、公的年金(厚生年金と国民年金)にとって重要な一年となります。2004年のマクロ経済スライド(※2)の導入以降、公的年金の保険料は一定の水準(厚生年金:18.3%、国民年金:16,900円)に固定されていますが、一方、年金額は調整(減額)が続く結果、特に国民年金(基礎年金)が将来的に大きく落ち込む見込みとなっています。そこで、今回の財政検証では、国民年金(基礎年金)の大幅な減少を抑えるための方策を、国民の納得を得られる形で打ち出せるかがポイントとなります。厚生労働省は財政検証において、次の5項目のオプション試算(※3)を行う予定です。
①被用者保険の適用拡大
②国民年金の45年化
③国民年金と厚生年金の調整期間の一致
④在職老齢年金の廃止
⑤標準報酬月額の上限引き上げ
では以下、①~⑤について順に見ていきましょう。
(※1)公的年金の長期にわたる財政の健全性をチェックするために行う検証のことで、社会・経済の変化を踏まえながら原則5年ごとに実施される。
(※2)少子高齢化が進行しても財源の範囲内で給付を賄えるよう、財源に合わせて給付の水準を自動調整(減額)する仕組み。
(※3)財政検証に加えて行われる、年金制度の課題の検討に役立てるための検証作業。オプション試算の内容に沿って、公的年金の見直しが行われる。
①被用者保険の適用拡大
被用者保険とは会社員や公務員が加入する年金のことで、つまりは厚生年金のことです。2020年の年金制度改正法により、短時間労働者に係る被用者保険の適用(人数)要件が、2022年10月から101人以上へ、2024年からは51人以上へと拡大されてきました。また、個人事業所の適用業種についても、2022年10月から弁護士・税理士等の士業にも拡大されています。今回、これら人数要件の拡大を一層進めようというものです。場合によっては、人数規模を問わず全事業所が加入対象となったり、短時間労働者の勤務時間週20時間以上、標準報酬月額88,000円以上という加入要件が撤廃される可能性もあります。要件の緩和・撤廃によって、被保険者数の増加⇒保険料収入の増大により、年金財政の健全化促進を図る狙いがあります。
②国民年金の45年化
現在、自営業者やフリーランス等は国民年金に20歳から60歳まで加入し、保険料を40年間払うことになっています。これを20歳から65歳まで加入し保険料を45年間払うことに変更し、年金額の増額を図るものです。国民年金の保険料(月額)は令和6年価格で16,980円なので、支払い期間が5年延長すると保険料は累計で、16,980円×12ヶ月×5年=1,018,800円、と約100万円増えることになります。(ただし、国民年金保険料は社会保険料控除の対象なので、所得税+住民税の税率が30%の人で実質負担増は70万円ほどです。) 他方、受け取れる国民年金(基礎年金)額は令和6年価格で816,000円ですが、保険料納付期間の延長により12.5%(45年/40年=1.125)増の918,000円となります。約10万円の増額です。メディア等では保険料負担の100万円増ばかりクローズアップされていますが、年金の受取り額が増える点にも注目すべきです。5年分の保険料の実質増加額を70万円、1年分の国民年金の実質増加額(税・社会保険料控除後)を9万円とすると、70万円÷9万円=約8年で元が取れる計算です。決して損な話ではないと思います。
③国民年金と厚生年金の給付調整期間の一致
マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、国民年金と厚生年金がそれぞれの勘定で財政均衡するまで続きます。国民年金は厚生年金に比べ財政状況が悪いため調整期間が長期化(20年以上)し、結果、国民年金(基礎年金)の将来の給付水準は厚生年金に比べ相当低いものとなります。2019年財政検証において、厚生年金の給付水準は2047年に向け実質ベースで約2割の減少見込みでしたが、国民年金(基礎年金)では約3割の減少見込みとなっています。そこで今回、国民年金と厚生年金で別々に財政の均衡を目指すことを止め、国民年金と厚生年金を一体で財政の均衡を目指す形に改めようというものです。これにより、国民年金(基礎年金)の調整期間は10年以上短縮され、現状の見通しよりも高い水準で給付が均衡します。一方、厚生年金の調整期間は長期化し、現状の見通しよりも低い水準で給付が均衡することとなります。
④在職老齢年金の廃止
在職老齢年金(在老)とは、働きながら厚生年金を受給している人が、厚生年金の月額(基本月額)とボーナスを含む年収の月額相当額(総報酬月額相当額)との合計で50万円を超えた場合、超えた額の1/2に相当する厚生年金を支給停止する仕組みのことです。(※4) (国民年金は支給停止の対象となりません。)この仕組みは、高齢者の就労意欲を削ぐと以前から批判されており、見直しが求められていました。また、政府は受給期間を遅らせることで年金額を増額する「繰り下げ受給」を推奨していますが、在老で支給停止された部分は繰り下げの対象外です。これは「繰り下げ受給」の増額効果を減退させるものであり、政府の方針に逆行しています。私は在老は今回、全面的に撤廃されるべきと考えます。
(※4)支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額ー50万円)×1/2
⑤標準報酬月額の上限引き上げ
標準報酬月額とは、厚生年金保険料の額を計算する際の元となる給料(保険料額=標準報酬月額×保険料率)のことで、被保険者(会社員や公務員)の4月~6月の給料の平均額から決定されます。標準報酬月額の決定にあたっては、厚生年金の全被保険者の標準報酬月額の平均の2倍を上限(現行65万円)とするルールがあります。今回、この上限を引き上げようというものです。政府は、上限に抵触している高収入の会社員に現行の上限を超える高額な保険料を負担させれば、年金の財源を増やすことができます。高収入の会社員も年金額が増えるので、ウィン・ウィンとなります。ただし、保険料の半分を負担する企業側の反発が予想されます。
以上、2024年の財政検証において見直しが予想される5項目について見てきましたが、今後①~③を中心に具体化に向けた検討が進められると思います。