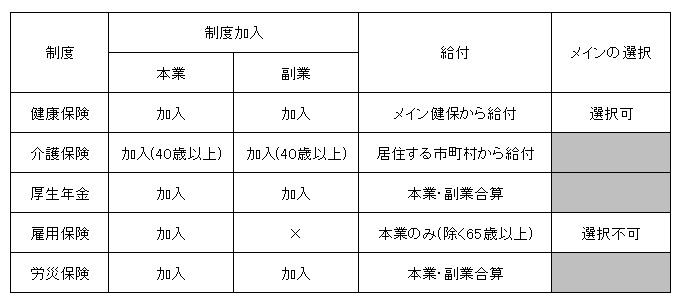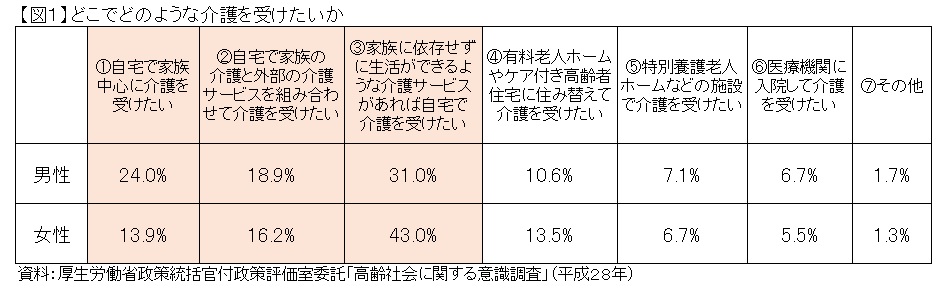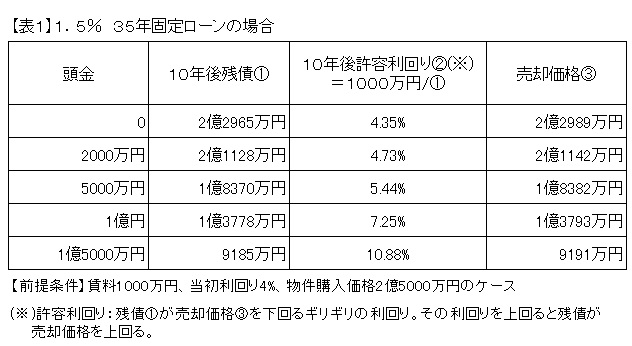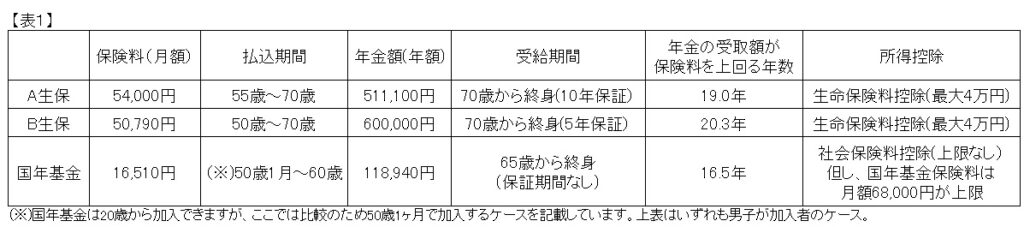先日の朝日新聞で、金融派生商品を組み込み高い利回りを売り物にした仕組み債の販売が地銀で増えており、金融庁が問題視しているとの報道がありました。そもそも、仕組み債の「仕組む」というワードに、あまりいいイメージはないですよね。「仕組まれた罠」、とか使ったりします。そこで、今回は仕組み債の闇に光を当ててみたいと思います。
朝日新聞では仕組み債の損益の概要を、次のように説明しています。
①株価が上昇し判定日に早期償還判定水準を超えていたら、早期償還され以後満期まで利息は得られない。
②株価が下落し元本割れ判定水準を1度でも下回ったら、満期日に元本割れで償還される。
③株価が早期償還判定水準と元本割れ判定水準の間で推移した場合は、満期まで高い利回りが受け取れ、元本も満額で償還される。
文字で書くと分かりにくいですが、要は仕組み債を購入した顧客は、株価が一定のレンジ内に収まっていれば勝ち(収益を得る)となり、株価がレンジを外れて上へ行ったり下に行ったりしたら負け(損失を被る)となります。これと似たような話、以前どっかで聞きませんでした? そう、「手作りオプションで遊ぼう」でご紹介した「ストラドル」にそっくりですよね。そうなんです。仕組み債は、ストラドルのようなオプション等の金融派生商品を仕組んだ債券なんです。仕組み債を購入した顧客は、株価が一定のレンジ内に収まれば高い利回りを享受でき「勝ち」となるので、「ストラドルの売り手」に相当します。実際はストラドルの様なプレーンなオプションではなく、経路依存型とかエキゾチックと呼ばれる複雑怪奇なオプション等が仕組まれていますが、基本的な構造は同じだとお考えください
仕組み債を買った顧客は、債券を買うのと同時にオプションを売っています。ここが1番目の問題点です。恐らく、顧客は自分がオプションを売ったことを自覚していないし、仲介者である地銀の営業担当者も、そのことを十分説明していないでしょう。また、顧客が売るオプションですが、その価格が証券会社から開示されることはありません。ここが2番目の問題点です。顧客は適正価格がいくらか知らないまま、証券会社の言い値でオプションを売らされます。顧客は知らないうちに安値でオプションを売らされた挙句、巨大なリスクを背負わされているかもしれないのです。
仕組み債は高利回りをセールスポイントとして販売されます。しかし、高利回りの種を明かせば、何のことはない。自分が売ったオプションの料金を、利息として受け取っているだけです。それも、オプションを叩き売りした結果の、すずめの涙ほどの利息かもしれません。
今、発効価格100円の5年物債券があるとしましょう。マイナス金利の昨今、通常であれば利率は0%です。そこで、証券会社は債券の購入者である顧客に、日経平均のオプションを15円で売らせます。証券会社は、オプションの料金を一度に顧客に支払ってもいいですが、ここでは1年に3円ずつ5年に亘って支払うことにします。顧客の口座には毎年オプション料が3円入金されます。これが、年利3%の高利回り5年物債券の正体です。
でも、オプションの適正価格が25円だったらどうでしょうか。本当なら5%の利息がもらえるはずです。この例では、100円あたり25円ー15円=10円(10%)が証券会社に抜かれていることになりますが、実際のところは開示がないので確認のしようがありません。ただ、オプションは満期までの期間が長いほど、価格は高くなります。現在東証で取引されている日経平均オプションは4月限までです。満期が5年先のような特殊なオプション価格は相当高いはずです。
冒頭あったように、金融庁も仕組み債のコストが不透明であるとして問題視しています。欧州では仕組み債のコストは、販売価格と公正価格の差額として開示されているとのことです。
仕組み債の販売額が伸びているということは、マイナス金利の世の中にあって、それだけ個人投資家のニーズが強いということです。証券会社はそのニーズに付け込むような真似はせず、仕組み債に仕組まれた金融派生商品の販売価格と適正価格、そしてリスクを明示した上で、正々堂々と顧客に販売してほしいと思います。
仕組み債を購入する個人投資家も「仕組み債」と聞いたら、まずは「怪しい」と警戒しましょう。そして説明を聞いて理解できないものには近付かないことです。