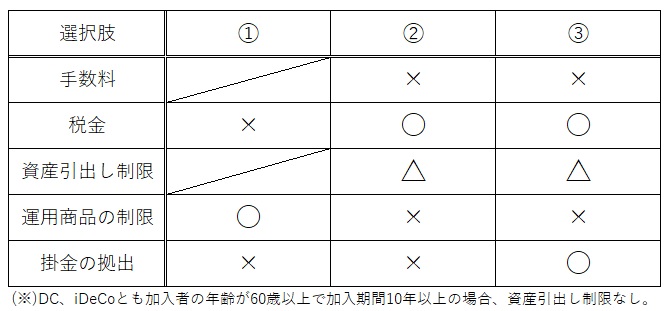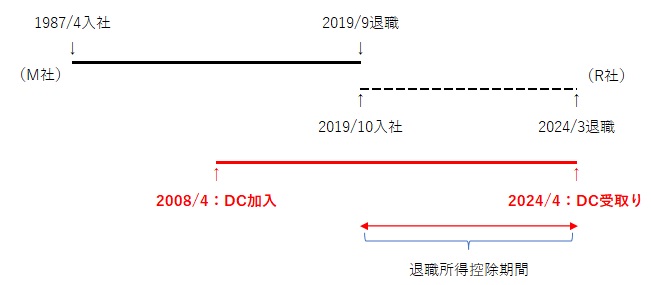10年以上も前の話ですが、三菱UFJ信託銀行の調査情報2012年3月号に「資産リターンの季節性と投資戦略」というユニークなレポートが掲載されました。今回は、このレポートのサマリーをご紹介したいと思います。
株式などの資産リターンの季節性を調べると、投資家は上半期(冬~春)にリスクを追求し、下半期(夏~秋)にリスクを回避する傾向があるそうです。この季節性の発生原因は、夜の長さの変化による季節性感情障害にあると筆者は見ています。そして、この季節性に着目することで、パフォーマンスを向上できる可能性があることが示されます。
バブル崩壊後の1990年1月から2009年12月の日本株のリターンを検証すると、1~6月と7~12月の期間に分けた場合、上半期がプラスリターン、下半期がマイナスリターンと極端な差が生じていることが分かります。なぜ、このようなリターン格差が生じるのか。1~6月と7~12月の2つの期間で最も異なるものは何か。それは夜の長さだと筆者は言います。冬至から夏至に至る期間と夏至から冬至に至る期間に、この2つの期間はぴったり一致しているからです。人間が秋から冬にかけて精神的に不調となる季節性感情障害(SAD)や冬季うつ(winter blue)といった病気が知られていますが、発症のきっかけとして夜の長さが関係していると言われています。
Kamstra et alは2003年の論文「冬季うつ:SAD株式市場サイクル」で夜の長さと株式市場リターンの季節性に関係があることを発見し、それをSAD効果と名付けました。また、Kamstra et alは2011年の論文「季節性に対応した資産配分:投資信託資金流入量からの証拠」で、直接SAD患者のデータから株式市場のリターンの季節性を検証しています。この論文において、秋に株式投信からMMFや債券投信に資金が移動し、春には再び株式投信に戻ること、そしてこの資金フローにSAD発生/回復変数が強く関係することを明らかにしました。
秋が来て日が短くなることが投資家のSAD発生を誘発し、SADは抑うつを招き、抑うつは投資家をリスク回避に誘う。SADのような季節性抑うつ症状は(程度の差はあれ)多くの人に現れるので株式市場はその影響を免れないと、この仮説は考えます。
レポートでは最後に資産リターンの季節性を利用した投資戦略が紹介されます。スイッチング戦略と筆者が呼ぶもので、リスク資産に高いリターンが期待できる上半期はリスク資産で運用し、リスク資産のリターンがマイナスになる可能性の高い下半期は安全資産にシフトするという単純な手法です。レポートではこの投資戦略の有効性も検証されています。
ほったらかし投資をモットーとする私の立場でスイッチング戦略はお薦めするものではありませんが、複数の投資戦略を組み合わせて市場に臨んでいる投資家の方にはアイデアとして面白いかもと思い、今回紹介させていただいた次第です。