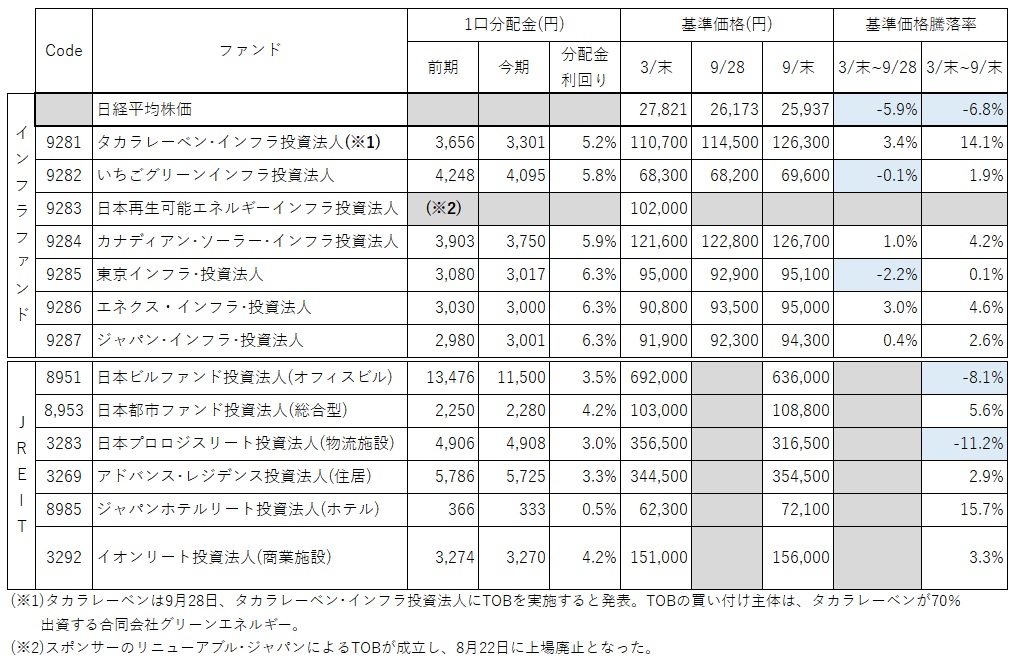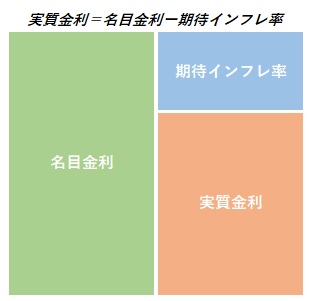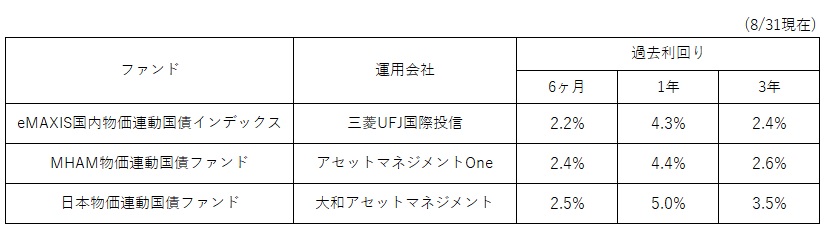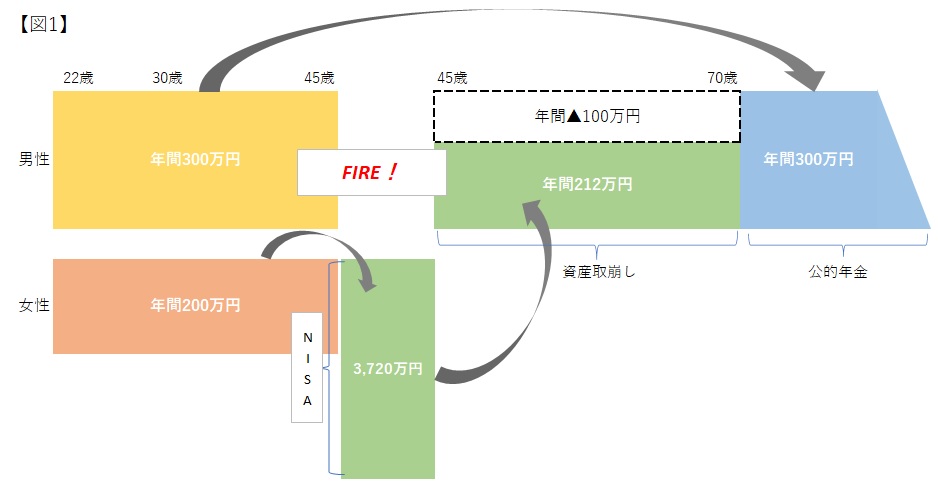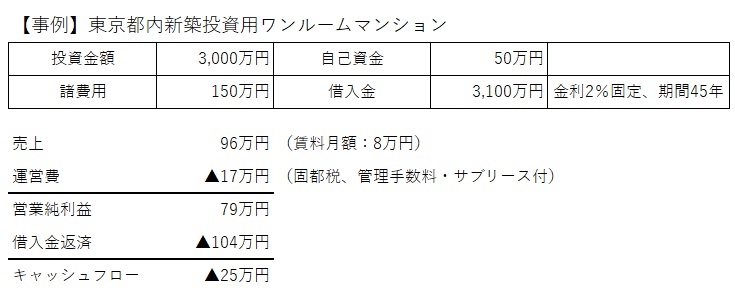生命保険の取り扱いについては、税務面を初め注意を要する事項がたくさんあります。私は税理士ではありませんので、あくまで一般論としての情報提供となりますが、生命保険の税務上のポイントにつきお話したいと思います。
1.入院給付金
被保険者=被相続人が一定の入院期間を経て死亡した場合、死亡保険金だけでなく入院給付金(場合によっては手術給付金や通院給付金等)が支給されることになります。しかし、この2つの給付金は税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。入院給付金の受取人が被相続人の場合、入院給付金は相続財産として遺産分割の対象になりますが、(みなし相続財産として非課税枠が設けられている死亡保険金と違い、)入院給付金には相続税の非課税枠の適用はありませんので要注意です。
入院給付金の受取人が被相続人以外の場合は、相続税の課税対象とはなりません。入院給付金は死亡に起因して支給されるものではなく、入院によって支払われる受取人固有の財産だからです。尚、身体の傷害に伴い支払われる給付金は所得税の課税対象となりませんので、入院給付金に所得税は課税されません。
2.医療保険の契約者変更
子供が学生の間は親が医療保険の契約者として保険料を払い、子供が社会人になったタイミングで子供に契約者を変更することがあります。ここで疑問に思うのは、それまで親が払ってきた保険料について、税金の問題は生じないかということです。税務署に贈与と見なされるリスクが心配です。結論から言いますと、契約者変更の時点では贈与税はかかりません。医療保険の権利だけを持っていても受取る給付金の額が決まっておらず、課税の仕様がないからです。
しかし、その後契約を解約して解約返戻金や満期保険金を受取った時点で、所得税が課税されることになります。また、解約返戻金等のうち親が負担した保険料に起因する部分については贈与税が課税されます。尚、解約返戻金や満期保険金のない掛捨てタイプの医療保険では、契約者変更しても税金はかかりません。
3.リビングニーズ特約
医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合に、契約している死亡保険金の全部(上限3,000万円)又は一部を生前に受取ることができる特約をリビングニーズ特約といいます。特約といっても追加の保険料は不要のため、多くの方が利用されています。リビングニーズ特約を利用して受取った生前給付金は、非課税所得に該当するため、所得税はかかりません。そのため、余命宣告を受けた方の家族は、「お父さんが保険料を払ったんだから、好きなだけお金を使っていいのよ」と、保険金の全額を引き出すこともあります。しかし、余命宣告を受けた方が海外旅行に行ったり、フランス料理を食べたりと、お金を使うにも限度があります。結局、大半のお金が未使用のまま相続財産となります。ここで注意したいのは、リビングニーズ特約はあくまで生前給付のため死亡保険金とは見なされないことです。法定相続人×500万円の相続税の非課税枠は適用されません。リビングニーズ特約の給付金は、使用可能な金額を請求し使い残しのないようにしたいものです。
4.代償分割
代償分割とは、不動産等の分割しにくい資産を相続した場合に有効な遺産分割方法です。複数の相続人のうち、特定の相続人がその遺産を相続する代わりに、他の相続人に対し一定の代償資産(例えば現金)を交付します。被相続人の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合や、事業などに利用する事業用不動産を相続する場合などに多く利用されます。
代償分割に使う現金を用意する器として、終身保険が使われます。相続人が兄弟2人のケースで(父親は既に死亡)、母親が兄には自宅(評価額2,000万円)、弟には定期預金1,000万円を相続させたいと考えているとしましょう。しかし、このままでは弟が兄に対し不公平だとして、遺産分割に納得しない可能性があります。その場合、最悪、兄は自宅の売却を迫られるかもしれません。
そこで、母親は別途、自身を契約者=被保険者、兄を受取人とする終身保険に1,000万円加入しました。母親の相続が発生すると、死亡保険金1,000万円が兄に支払われます。これは相続財産ではなく兄固有の財産です。そして、兄はこの1,000万円を代償金として弟に交付すれば、兄弟とも均等な資産を受取ることができます。
では、次のようなケースはどうでしょう。兄に3,000万円の死亡保険金、弟に1,000万円の定期預金が配分され、兄が保険金のうちの1,000万円を弟に交付するケースです。先のケースと同じように見えますが、注意が必要です。死亡保険金は相続財産でないため、2番目のケースでは兄は相続財産を受取っていないことになります。遺産分割の対象でない兄から弟に交付された1,000万円は相続財産の代償金とはみなされず、単なる贈与として課税されますので要注意です。