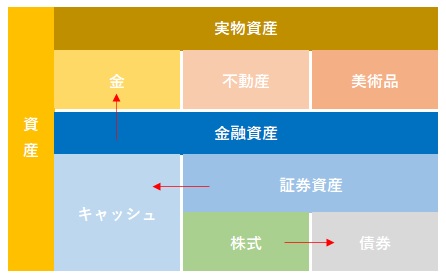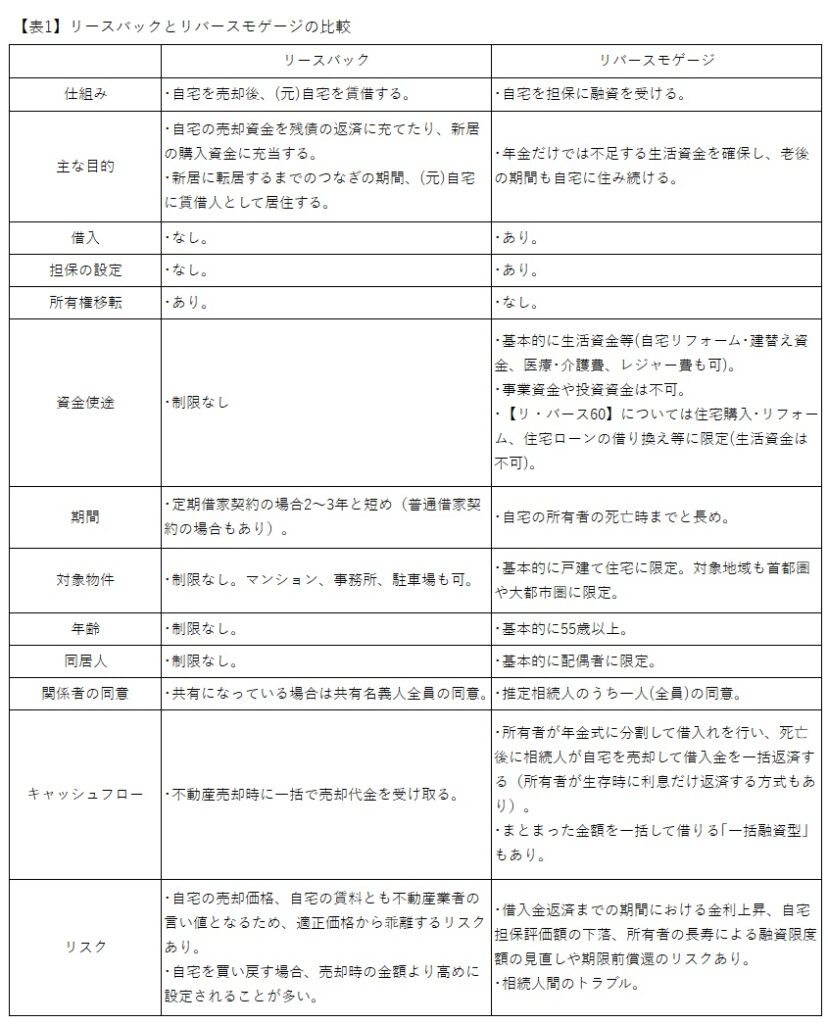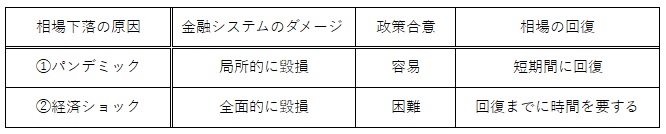「医療保険を考える」では、医療保険に入る意味を「時間を買う」ことにあるとご説明しました。それでは、がん保険の場合はどうでしょうか。まずは、多くの病気の中でなぜ「がん」だけが単独の保険商品となっているのか、その点から考えてみたいと思います。がんの特徴として、その死亡率の高さがあります。また、長期間に及ぶ治療と激しい副作用。そして、再発リスク。これらがん固有の特性に対応するためがんに特化した保険が生まれ、これまで支持されて来たと考えられます。
もっとも最近では医療の進歩により、がんの死亡率は低下傾向にあります。年齢要因を調整した「がん年齢調整死亡率」は1995年の10万人あたり226人をピークに、2020年は148人まで低下しています。(国立研究開発法人/国立がん研究センター調査) また治療法の変容により、がん治療は入院から通院で行うものへと変わってきています。平成8年から平成29年の20年間で、がん患者の平均入院日数は46日から17日まで短縮しています。そして通院での受療が増加しています。(厚生労働省患者調査) 背景には、腹腔鏡・胸腔鏡手術やロボット支援手術(ダビンチ・Hinotori等)の普及による患者の負担軽減(手術での傷が小さくなった)があります。従前は、放射線治療や抗がん剤治療を入院で行っていましたが、今では通院で行うことが主流となっています。
がんが再発した場合は治療による根治が困難なケースがあり、その場合はがんの進行を抑える、または痛みを和らげることが治療の目標となります。慢性病のような感覚で、がんという病との気長な付き合いが始ります。放射線や抗がん剤、ホルモン剤等の治療を組み合わせた集学的治療を受けることになりますが、長期間の治療は高額療養費を持ってしても家計に大きな負担となります。さらに厄介なのは、抗がん剤等の副作用による体力の低下で就業が困難となり、収入が減少ないし絶たれるリスクがあることです。
このように、がん保険は医療保険と違い入院・手術の保障だけでは不十分で、長期の通院と治療、さらには療養期間中の就業不能をカバーする総合的な保障が求められます。確かに、がん保険は保険事故をがんに限定しているため、医療保険に比べ給付を受けられる可能性は低いです。しかし、その分医療保険に比べレバレッジが高く、保険を活用するメリットは大きいと言えます。